
マンション管理士試験 の 10門
第8問
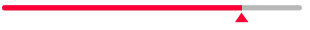
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

マンション管理士試験 の 10門
第9問
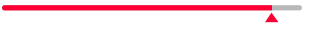
管理組合の総会及び理事会の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型) (以下「標準管理規約」という。)によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

マンション管理士試験 の 10門
第10問
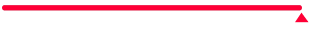
甲マンションの401号室の区分所有者Aが多額の債務をかかえたまま死亡し、Aに子B及び子Cの相続人がいた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。




